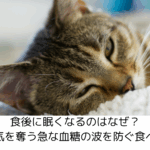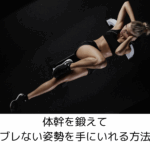「先生、冬だけじゃなくて夏でも足先が冷えるんです…」
接骨院でよく聞く相談のひとつが冷え性。特に女性に多い印象がありますが、実際は男性でも少なくありません。高校のバスケ部を見ていても、練習後に「手足が冷えて感覚が鈍い」と訴える選手がいました。若くても油断はできないんです。
今回は、冷え性を「食べ物」という切り口で考えてみます。体を温める栄養の話を、現場での体験談を交えながらお伝えします。
冷え性ってどういう状態?
冷え性とは、外の気温や活動量に関わらず、体の一部(特に手足)が慢性的に冷たく感じる状態を指します。原因はさまざまで、
- 血流が滞っている(運動不足や筋力低下)
- 自律神経のバランスが乱れている(ストレス・睡眠不足)
- 栄養不足(特に鉄分やタンパク質の不足)
- 過度なダイエット
などが考えられます。

「血の巡り」と「熱をつくる材料」が不足すれば、当然体は冷えてしまいます。私が往診先で見てきた高齢者の方々も、食欲が落ちて栄養が偏ると一気に冷えが強くなり、夜眠れなくなるケースがありました。
体を温める栄養素と食べ物
1. 鉄分
血液を作るのに欠かせないミネラル。鉄分不足は「スポーツ貧血」にもつながり、冷えを悪化させます。
おすすめの食材:赤身の肉、レバー、カツオ、アサリ、大豆製品、ほうれん草。
→ 高校野球部で鉄不足だった選手にレバーを使った家庭料理を勧めたところ、数週間で持久力が戻ったことがあります。
2. タンパク質
筋肉を作り、体の中で「熱を生み出す工場」の役割を果たします。冷え性の人は意外とタンパク質が足りていません。
おすすめの食材:鶏むね肉、魚、卵、豆腐、納豆、ヨーグルト。
スポーツトレーナー専門学校の授業で学生に伝えるのは「おにぎりだけで練習すると体は冷えるよ」という話。エネルギーだけでなく、筋肉の材料を摂らなければなりません。
3. ビタミンE
血管を広げて血流をスムーズにする働きがあります。
おすすめの食材:アーモンド、ひまわり油、かぼちゃ、うなぎ。
4. ショウガ・ネギ類
いわゆる「体を温める食材」として昔から使われています。ショウガは血管を広げ、発汗を促す作用が知られています。
→ 私自身、冬の往診前にはお茶にすりおろしショウガを少し入れて飲むのが習慣です。体の芯からじんわり温まります。
冷えを招く食べ物もある
一方で、冷えを悪化させる食習慣もあります。
- 冷たい飲み物(氷入りジュースやビールのがぶ飲み)
- 甘いお菓子(血糖値スパイクで逆に血流が乱れる)
- 極端な糖質制限(エネルギー不足で代謝が落ちる)

患者さんの中には「水分を控えすぎて血流が悪くなる」ケースもありました。水分は常温のお茶や白湯で、こまめに補うのが良いです。
*血糖値スパイクとは?
食事をした後に、血糖値(血液中のブドウ糖の量)が 急激に上がり、そのあと急激に下がる現象 のことをいいます。
通常、食事をすると血糖値はゆるやかに上がって、インスリンというホルモンの働きでエネルギーとして細胞に取り込まれます。ところが、甘いものや白米・パンなど血糖値を上げやすい食品を一気に食べると、急上昇(スパイク=とがった山のように急に上がる)が起き、その後インスリンが大量に出て急降下してしまいます。
なぜ良くないのか?
- 眠気やだるさ が出やすい
- 集中力が落ちる
- 長く続くと 糖尿病や動脈硬化のリスク を高める
例えるなら…
血糖値スパイクは、ジェットコースターのようなもの。
一気にグッと上がって、ガクンと下がる。その繰り返しが体に負担をかけます。
食べ方の工夫で冷えを和らげる
- 朝食を抜かない
朝食を取らないと体温が上がらず、一日中手足が冷える人が多い。発芽玄米のおにぎり+味噌汁+卵焼き、この組み合わせはおすすめ。
- よく噛んで食べる
噛むこと自体が熱を生み、血流を促す。
- 旬の食材を選ぶ
冬野菜(大根、カブ、白菜)は体を温め、夏野菜(トマト、きゅうり)は体を冷やしやすい。季節に合った食事が自然と冷え性対策になります。
実際の現場での体験談
- 高齢者スポーツ教室での話
「冬になると足が冷えて動きたくなくなる」と訴える方がいました。昼食がパンとコーヒーだけだったので、具だくさんの味噌汁を提案。次の週、「夜も足が冷えにくくなって眠れるようになった」と喜ばれました。
- 接骨院の患者さん
冷えと肩こりで通っていた女性。食事内容を聞くと、野菜サラダ中心でタンパク質がほとんどなし。鶏肉や魚を加えるようアドバイスすると、数週間後「体が温まりやすくなった」と報告してくれました。
まとめ|冷え性は食べ物で変えられる
冷え性は「体質だから仕方ない」と思い込む人が多いですが、実際は食生活の影響が大きいです。
鉄分やタンパク質をしっかり摂ること、温かい食材を意識して選ぶこと。それだけで体の芯から温まり、肩こり・腰痛・疲労感も和らいでいきます。
冷えで悩んでいる方は、まず食卓を見直してみてください。今日の夕食に、ショウガを加えた味噌汁や、魚の塩焼きを一品足すだけでも違います。
接骨院で施術を受けることももちろん効果的ですが、日々の食事が土台です。栄養の積み重ねで、冷えに強い体をつくっていきましょう。
新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市
#冷え性改善 #冷え性対策 #冷え性食べ物 #冷え性予防 #温活