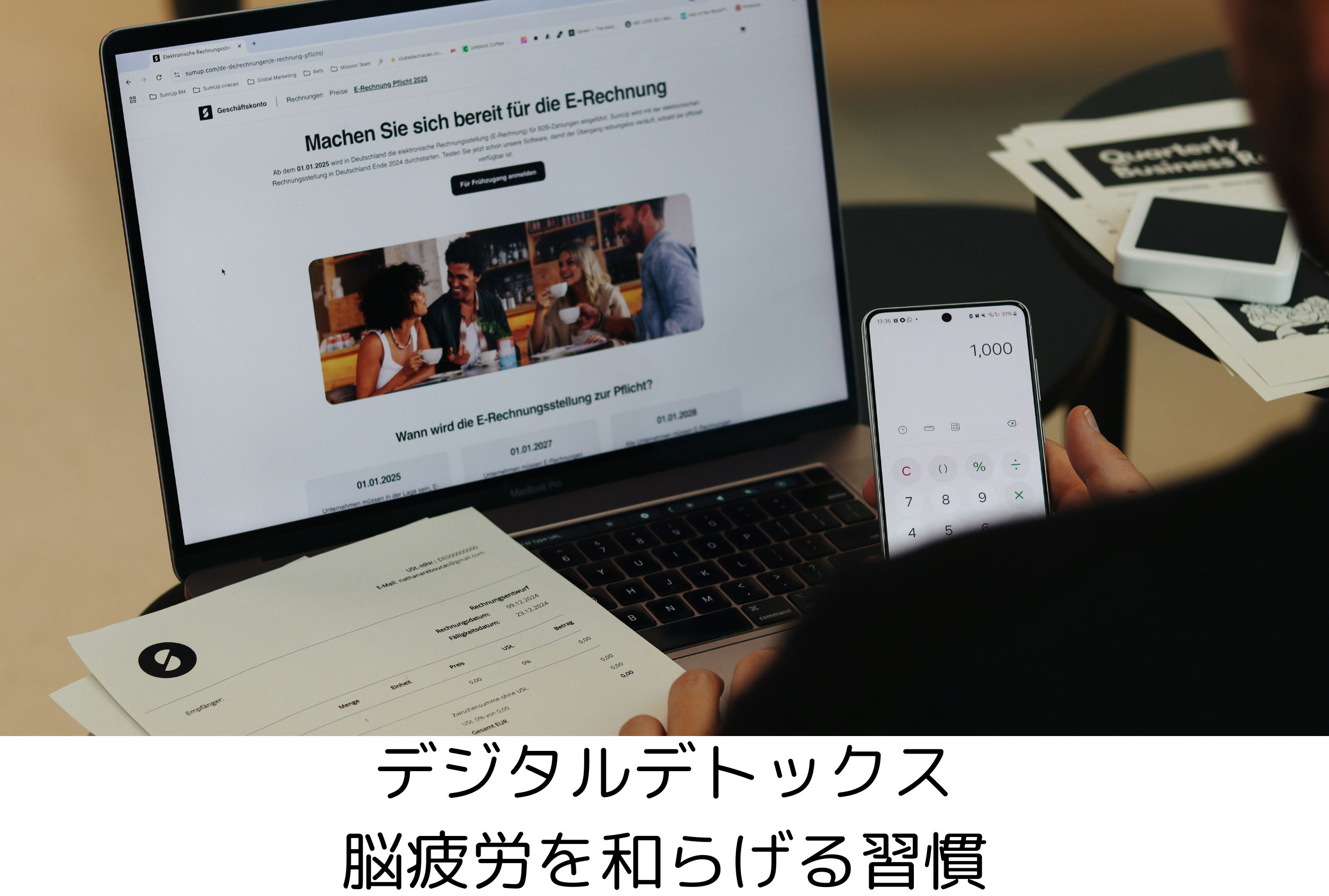「寝たのに頭が重い」「スマホを見ていたらあっという間に夜中になっていた」
こうした声、接骨院でもよく耳にします。患者さんの中には「肩こりと頭痛で来たけれど、よくよく話を聞いたら原因はスマホ漬けの生活だった」という方も少なくありません。
私自身も恥ずかしながら、ブログ記事を書きながらスマホで株価をチェックし、そのままYouTubeを流し見してしまい…気づいたら午前1時。翌朝、頭がボーッとして「ああ、これは完全に“脳疲労”だ」と痛感したことがあります。
現代人にとってデジタル機器は欠かせないもの。でも、上手に距離をとらないと脳が休む時間を失い、疲労が積み重なります。そこで今回は「脳疲労を和らげるデジタルデトックス習慣」を、現場の体験を交えながらご紹介します。
デジタル疲れがもたらす脳の不調
スマホやパソコンの画面を長時間見続けると、目や首だけでなく脳にも負担がかかります。
• 睡眠の質が落ちる
• 集中力が続かなくなる
• 気分が不安定になる
専門学校の授業で学生に「昨日何時間スマホを触っていた?」と聞くと、平気で「6時間です」と答えます。若さゆえに平気そうな顔をしていますが、試験の時期になると「頭が重くて集中できません」と相談に来る。脳が疲れている証拠です。
習慣① 寝る前の“スクリーン断ち”
脳疲労の大きな原因のひとつが、寝る直前までのスマホ使用です。ブルーライトが睡眠リズムを狂わせ、深い眠りを妨げます。
接骨院の患者さんに「寝る前1時間はスマホを枕元に置かない」と伝えたら、「最初はソワソワしましたが、1週間で寝つきがよくなった」と話してくれました。私自身も寝室にスマホを持ち込まない日を作るようにしたら、翌朝の頭の軽さに驚きました。
習慣② 通勤・移動時間の“耳デトックス”
電車やバスでスマホをいじるのが習慣になっている方も多いですが、あえて耳だけを使う時間に切り替えてみるのも良い方法です。
音楽やラジオを聴く、あるいは“無音”で外の景色を眺める。
高校野球部の遠征バスでも、選手たちはずっとスマホに夢中。そこで「今日は外の景色を見ながら深呼吸してみたら」と言ったら、到着後の練習で動きが軽い選手が多かった。視覚情報を減らすだけで脳の回復につながるんですね。
習慣③ 食事中は“ながらスマホ禁止”
「食事中にスマホを見ていると、味がわからなくなる」これは多くの方が実感しているはず。実際、脳は同時処理が苦手で、味覚の感覚が鈍くなります。
往診先のお宅で、ご夫婦が「食事中はテレビを消して会話をするようにしたら、ご飯が美味しく感じるようになった」と話してくださいました。食べ物の香りや食感を意識すること自体が脳のリフレッシュになるのです。
習慣④ “デジタル断食デー”をつくる
完全にスマホやPCを断つのは難しいですが、半日〜1日だけでも“デジタル断食”をしてみると頭がすっきりします。
私も試しに日曜日の午前中だけスマホを封印し、自宅周辺の草むしりをしてみました。すると普段は気づかない鳥の声や風の音に集中できて、不思議と気分が軽くなりました。患者さんにも提案したら「孫と遊ぶ時間が増えて幸せ」と喜んでいました。
習慣⑤ アナログを味方にする
スマホでスケジュールやメモを管理するのも便利ですが、あえて紙の手帳やノートを使うと脳が休まります。
ある専門学校の学生に「授業ノートは手で書くように」と伝えるのですが、これは単に昔ながらのやり方を押しつけているのではありません。手を動かすことで脳が情報を整理しやすくなり、頭の疲れを軽減できるからです。
習慣⑥ 休養の質を高めるアクション
デジタルデトックスをして空いた時間を、質の良い休養にあてると脳の回復効果が倍増します。
• 深呼吸や軽いストレッチ
• ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる
• 短い昼寝(15〜20分)
体育館での高齢者運動教室で、休憩中に「スマホではなく深呼吸の時間にしましょう」と伝えたら、その後の体操で皆さんの動きがなめらかになったのが印象的でした。
私の現場での実感
接骨院に来ていた40代男性の会社員。首と肩の凝りが強く、頭痛も頻発していました。話を聞くと、仕事でもプライベートでも常にスマホとPC。
そこで「寝る前の30分はスマホを見ない」「昼休みに10分外を歩く」を提案したところ、2週間で「頭痛が減り、集中力が戻った」と嬉しい報告をいただきました。
脳を休ませる1日のデジタルデトックス簡単ルーティン
「やった方がいいのは分かるけど、結局どう取り入れればいいの?」
そんな声を患者さんや学生からよく聞きます。そこで、現場で実際に伝えている“シンプルなルーティン”を紹介します。無理に全部やる必要はありません。どれかひとつ選ぶだけでも脳の休養効果が出ます。
🌅 朝:スタートは“デジタルフリー”
• 起きてすぐにスマホを手に取らない
• まずはカーテンを開けて朝日を浴びる
• コップ1杯の水を飲みながら深呼吸
👉 朝イチでニュースやSNSを見てしまうと、脳が一気に情報でいっぱいになります。患者さんに「朝はスマホより窓を開けろ」と伝えたら、「気分が全然違う」と笑顔で話してくれました。
🌞 昼:仕事や学業の合間に“スクリーン休憩”
• 1時間ごとに画面から目を離し、遠くを10秒見る
• 昼休みはスマホを置いて、5分だけ外を歩く
• 食事中は「ながらスマホ」をやめ、味や香りに集中する
👉 高校野球部の選手たちにも「昼はスマホを置いて外を歩いて」と言っています。実際にやった子は「午後の練習で足が軽かった」と驚いていました。脳に酸素と新鮮な景色をプレゼントするイメージです。
🌙 夜:眠りにつながる“リセットタイム”
• 寝る1時間前にスマホ・パソコンを手放す
• 紙の本や日記を書くなど“アナログ時間”に切り替える
• ぬるめのお風呂に入り、ストレッチや深呼吸でリラックス
👉 接骨院に通う40代会社員の患者さんに「夜は紙の本を読んでから寝てください」と伝えたところ、「翌朝の頭の重さがなくなった」と喜んでいました。小さな習慣が、翌日の頭の冴えに直結します。
私の場合はよく「寝ながら本を読んでいたら、うとうとした瞬間にハードカバーが顔面に直撃!夢の世界に入る前に、本から“強制終了”の合図をもらっています。」
続けるコツは「完璧を目指さない」
「全部やらないと意味がない」と思うと続きません。
私自身も、忙しい日は夜のスマホ断ちだけを守るようにしています。それでも翌朝の感覚が全然違うんです。
患者さんにも「できたことを1つノートに書いてみてください」と伝えています。小さな達成感の積み重ねが、習慣化の一番の近道です。
まとめ:デジタルとの距離をほんの少し変える勇気を
デジタルは便利ですが、脳にとっては強い刺激です。休む時間を意識的につくらないと、気づかぬうちに疲労が蓄積していきます。
朝はスマホを置いて朝日を浴びる。昼は画面から目を離して歩く。夜は紙の本と深呼吸でリラックス。寝る前のスクリーン断ち、通勤中の耳デトックス、食事中のスマホ禁止、デジタル断食デー、紙の手帳、そして深呼吸や入浴。どれも大げさなことではなく、誰でもすぐに取り入れられる習慣です。
「ちょっとスマホを置いてみる」――その小さな一歩が、脳を休ませる勇気につながります。頭がすっきりすれば、体も心も軽くなる。その感覚を、ぜひ味わってみてください。
新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市