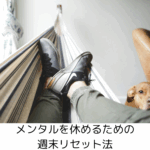「先生、最近ちょっとした段差でつまずいて、骨折しそうになったのよ」
外来で高齢の患者さんからよく聞く一言です。70代、80代になると骨折がきっかけで寝たきりになってしまう方も珍しくありません。私は柔道整復師として30年以上、多くの患者さんと向き合ってきましたが、骨密度を守ることは“人生の後半戦”を元気に過ごす最大のカギだと感じています。
今回は「加齢に伴う骨密度低下をどう防ぐか」を、運動、食事、生活習慣の観点から体験談を交えつつお伝えします。
骨密度はなぜ低下するのか?
人間の骨は一度作られたら終わりではなく、常に新陳代謝を繰り返しています。20〜30代でピークを迎え、40代以降は骨を作る働きよりも壊す働きが上回るため、少しずつ骨密度は低下していきます。特に女性は閉経後、ホルモンバランスの影響で急激に骨密度が落ちることがわかっています。
高齢者運動教室でも、骨密度検査の結果を見てショックを受ける方が多いんです。「先生、見た目は元気なのに骨がスカスカって言われちゃった」と笑いながらも不安そうな表情。骨の健康は“見た目”だけでは判断できないことを、改めて感じさせられます。
運動で骨を刺激する|筋肉と骨は仲良し
骨は負荷をかけることで強くなります。宇宙飛行士が地球に帰還すると骨密度が低下しているのは、重力による負荷がかからないから。つまり、適度に骨へ刺激を与えることが骨密度維持の秘訣です。
骨に効く運動の具体例
- ウォーキング:毎日20〜30分。腕を大きく振り、かかとから着地すると骨への刺激がしっかり伝わります。
- かかと落とし運動:その場で軽く背伸びして、かかとをストンと落とす。地味ですが骨に適度な衝撃を与えられる優れもの。
- スクワット:太ももの大きな筋肉を鍛えることで転倒予防にもつながる。
以前、体育館での高齢者運動教室で「かかと落とし運動」を指導したとき、ある男性が「こんな単純な運動で骨が強くなるなら毎日やるよ!」とニコニコ。数ヶ月後、骨密度の検査結果が改善しており、ご本人も「続けるってすごいね」と実感されていました。
栄養で骨を守る|カルシウムだけでは足りない
骨といえばカルシウム。これは誰でも知っています。ただし、カルシウムだけを意識して牛乳をガブガブ飲んでも、うまく吸収されなければ意味がありません。
骨を育てる栄養素
- カルシウム:牛乳、チーズ、小魚、豆腐など。
- ビタミンD:鮭、サンマ、干し椎茸。日光浴でも体内合成される。
- ビタミンK:納豆、ブロッコリー。骨の形成を助ける。
ある患者さんに「納豆は骨のサプリ」と話したら、それ以来毎日欠かさず食べるようになったそうです。その方、数年後の検査で骨量が維持されていて「先生、納豆パワー信じてるよ!」と笑顔でした。
生活習慣の落とし穴
骨密度に悪影響を与える生活習慣もあります。
- 喫煙:血流を悪くし、骨への栄養供給を妨げる。
- 過度な飲酒:カルシウムの吸収を妨げる。
- 極端なダイエット:必要な栄養が不足し骨がもろくなる。
接骨院に来られた40代の女性患者さん。「若い頃からダイエットでご飯をほとんど食べなかった」と話していました。検査すると骨密度が同年代よりも低く、日常生活での骨折リスクが高まっていました。痩せすぎ=健康ではない、という現実を物語っています。
転倒を防ぐ工夫も忘れずに
骨が強くても、転んでしまえば骨折のリスクはゼロではありません。特に高齢者は「転倒予防」がセットで必要です。
- 室内の段差やカーペットをなくす。
- 夜間は足元を照らすライトを置く。
- 下半身の筋肉を鍛え、バランス感覚を維持する。
高齢者運動教室で「片足立ち」を習慣にした方が「買い物袋を持っていてもふらつかなくなった」と話してくれました。小さな積み重ねが、大きな自信につながるのです。
専門家として伝えたいこと
骨密度は一度落ちたら戻らない、と諦めてしまう人が多いですが、実際には生活習慣を変えることで維持・改善できる可能性は十分にあります。
接骨院で患者さんと向き合っていて感じるのは、正しい知識よりも「継続の工夫」が大切だということ。ウォーキングも、納豆も、かかと落としも、楽しみながら続けることで未来の骨を守ることにつながります。
まとめ|「膝が笑う前に、骨を守ろう」
私自身、年齢を重ねるごとに「今日は階段が少し重たいな」と感じることが増えてきました。そんな時こそ「骨を意識する日常」が必要だと思っています。
骨は裏切りません。運動と栄養、そして生活習慣の工夫で、まだまだ元気に歩き続けられる体をつくっていきましょう。
新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市
#骨密度、#加齢、#骨粗鬆症、#運動、#ウォーキング、#カルシウム、#ビタミンD、#ビタミンK、#転倒予防、#接骨院、#新潟市