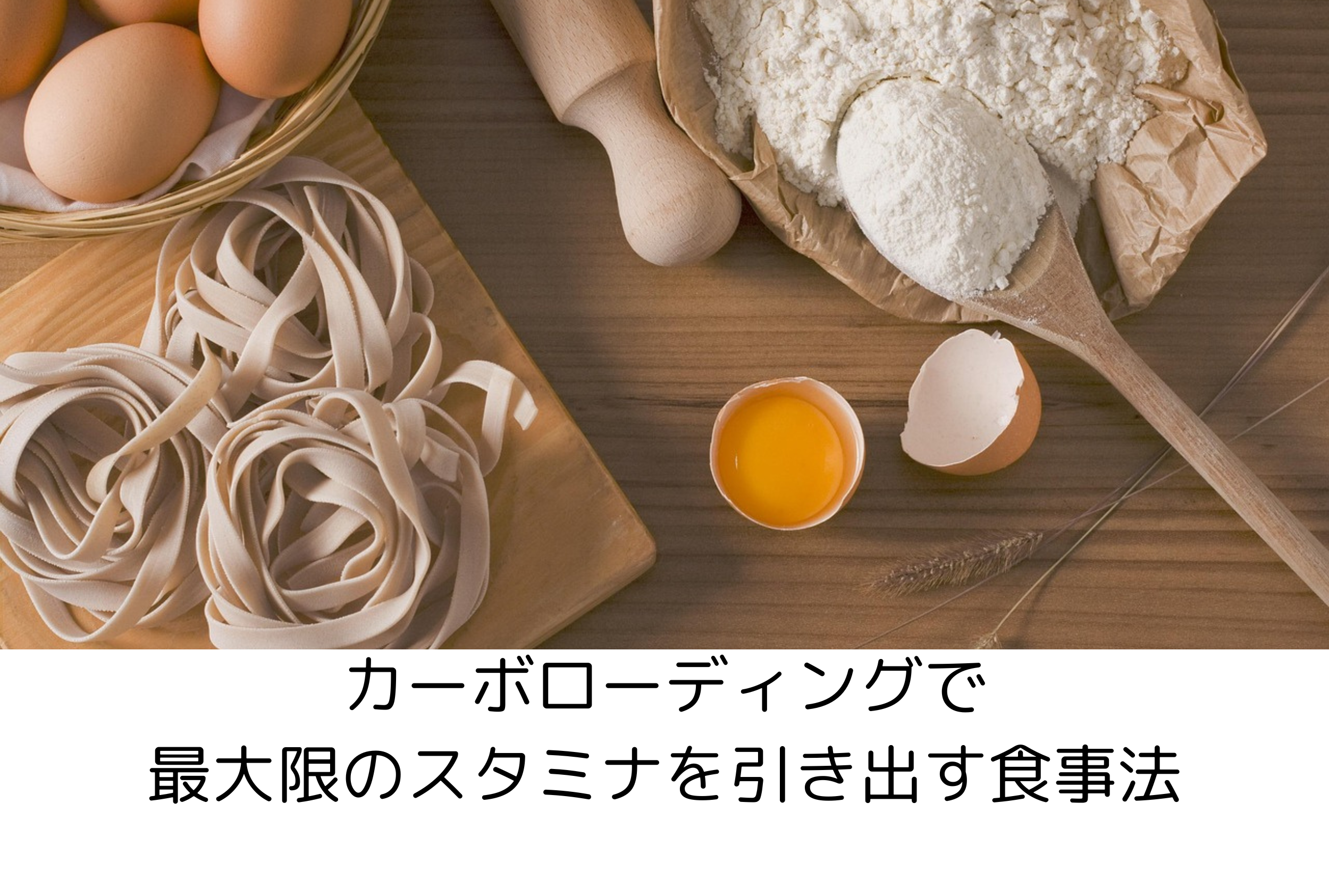炭水化物と持久力の関係
「練習はしているのに最後まで走りきれない」
スポーツ現場や接骨院でよく聞く悩みのひとつです。筋力やフォームに問題がなくても、スタミナ切れを起こす選手は少なくありません。その原因の多くは、実は「炭水化物の摂り方」にあります。
炭水化物を摂ると体内でグリコーゲンとして肝臓や筋肉に蓄えられます。これは身体を動かすためのガソリンのような存在で、持久系競技では特に重要です。グリコーゲンが枯渇すると「30kmの壁」と呼ばれる失速状態に陥ります。そこで注目されるのが 炭水化物の質とタイミング、そしてカーボローディング です。
カーボローディングとは?
カーボローディング(Carbohydrate Loading)は、レースや大会の数日前から意識的に炭水化物を多く摂取し、筋肉や肝臓にエネルギー源であるグリコーゲンを通常以上に蓄えておく食事法です。
簡単に言えば、試合前に「燃料タンクを満タンにしておく」準備のこと。
人の体は、炭水化物を食べるとブドウ糖に分解し、その一部をグリコーゲンとして筋肉や肝臓に貯蔵します。ただし貯蔵できる量には限界があり、体重70kgの成人でおよそ400〜500g程度。これだけでは、フルマラソンやトライアスロンのような長時間の競技を走り切るには足りません。
そこで、試合の2〜3日前から炭水化物の割合を高め、通常より1.5〜2倍のグリコーゲンを蓄えることで、後半までエネルギー切れを防ぐのがカーボローディングの狙いです。

カーボローディングの効果
- レース後半の「失速(30kmの壁)」を防ぐ
- 集中力を持続しやすくなる(脳も糖質を主な燃料にしているため)
- 疲労の蓄積が軽減され、パフォーマンスが安定する
実際、私がサポートした フルマラソンに挑戦する市民ランナーの患者さん も、「初めて30kmを過ぎても足が止まらなかった」と効果を実感していました。これまで毎回30km地点で失速していたそうですが、レース3日前からしっかり炭水化物を蓄えたことで、最後までペースを落とさず完走できたのです。

実践のポイント
- 開始時期:レースの2〜3日前から炭水化物を増やす
- 主食中心:白米、パスタ、うどん、パンなど消化の良いものを選ぶ
- 脂質を控える:揚げ物やクリーム系は胃もたれの原因になる
- 食べ過ぎない:必要以上の摂取は体重増加や消化不良につながる
- 前日は腹八分目:食べ過ぎで当日体が重くなるのを防ぐ

注意点
- 菓子パンやケーキのように脂質や砂糖が多い食品で炭水化物を摂ろうとすると、胃腸に負担がかかる
- 食物繊維の摂りすぎは当日お腹が張ってしまうことがある
- 糖尿病など代謝疾患がある方は、医師の指導なく行わないほうがよい
カーボローディングの目的
マラソンや長距離競技のように数時間以上続く運動では、通常のグリコーゲン量(約400〜500g)では足りません。レース直前に炭水化物を多めに摂り、筋肉内のグリコーゲン量を通常の1.5倍〜2倍に増やすことで、後半の失速を防ぎます。
実践方法
古典的には「前半で炭水化物を減らして枯渇させ、その後に大量に摂る」という方法がありましたが、疲労が残りやすいため現在は推奨されません。
現在一般的なのは レース3日前から炭水化物を意識して増やすシンプルな方法 です。
炭水化物の「質」でパフォーマンスが変わる
炭水化物と一口に言っても種類は様々です。
- 白米・菓子パン・砂糖 → 吸収が速く、血糖値が急上昇しやすい。瞬発的な力は出るが、エネルギー切れが早い。
- 玄米・そば・全粒粉パン → 消化がゆっくりで、持続的にエネルギーを供給。持久力向上に適している。

往診先の高齢の方で、朝食がパンと牛乳だけという方がいました。その後、玄米やさつまいもに置き換えていただいたところ、午後の疲れが減り「散歩が楽になった」と話してくれました。炭水化物の質を変えるだけで体力の安定感が出るのです。
炭水化物の「タイミング」で持久力が決まる
炭水化物は摂る時間帯によっても効果が変わります。
運動2〜3時間前
消化に時間がかかる炭水化物(玄米、パスタ)でグリコーゲンをしっかり貯めておく。
運動直前(30分〜1時間前)
バナナやおにぎりなど、胃に負担をかけずエネルギーに変わりやすいものを少量。
運動後30分以内
白米や果物など、吸収の速い炭水化物でグリコーゲンを補給。タンパク質を一緒に摂ると筋肉の修復も進む。
高校バスケ部での体験ですが、試合後にスポーツドリンクだけで済ませる選手と、バナナやおにぎりを食べた選手では翌日の疲労感がまったく違いました。タイミングを意識するだけで回復力に差が出るのです。
カーボローディングの食事例
朝食
- 白ごはん(茶碗2杯) ・焼き鮭 ・みそ汁 ・バナナ
昼食
- パスタ(トマトソース) ・鶏むね肉のソテー ・サラダ
間食
- おにぎり ・スポーツドリンク
夕食
- うどん+温泉卵 ・ほうれん草のおひたし ・フルーツ(みかんやりんご)
炭水化物を上手に摂る!目的別ランキング
🏃 スポーツ向け(持久力・試合前後の補給)
1位:白ごはん
消化が良く、エネルギーに変わるスピードが早い。試合前の主食に最適。
2位:バナナ
カリウムも豊富で筋肉の痙攣予防にも。運動直前や試合中の補給に使いやすい。
3位:パスタ(トマトソースや和風)
脂質が少なく、炭水化物量をしっかり摂れる。マラソン前のカーボローディング定番食。
4位:おにぎり
持ち運びやすく、消化も良い。具材は梅干し・鮭などが理想。
5位:じゃがいも
でんぷん質が多く、エネルギー補給に優れる。消化も軽い。

👵 高齢者向け(体力維持・消化に優しい)
1位:さつまいも
食物繊維とビタミンCが豊富。血糖値が急に上がりにくく、腹持ちも良い。
2位:オートミール
食物繊維が多く、少量でも満足感がある。牛乳やヨーグルトと合わせやすい。
3位:おかゆ(白米をやわらかく炊いたもの)
消化にやさしく、体調が悪いときでも食べやすい。
4位:りんご
果糖と食物繊維をバランス良く含み、整腸作用もある。皮ごとすりおろせば消化も良い。
5位:うどん
柔らかく消化が良い。体調不良時や胃腸が弱っているときにも適している。
👨👩👧 日常生活向け(仕事・学習・普段の活力)
1位:玄米
ビタミンB群やミネラルが多く、疲労回復を助ける。血糖値も安定しやすい。
2位:全粒粉パン
食物繊維や鉄分を含み、朝食や昼食に取り入れやすい。
3位:そば
GI値が低く、血糖値が急に上がりにくい。昼食におすすめ。
4位:とうもろこし
ビタミン類も含み、自然な甘みで子どもにも人気。
5位:ドライフルーツ(レーズン、デーツ)
少量でエネルギー補給ができ、デスクワークの合間の間食に最適。
- スポーツ向け → 白米・バナナ・パスタ・おにぎりなど「すぐエネルギーになる食品」
- 高齢者向け → さつまいも・オートミール・おかゆ・りんごなど「消化が良く体に優しい食品」
- 日常生活向け → 玄米・全粒粉パン・そば・とうもろこしなど「栄養バランスと持続力のある食品」
炭水化物は「太るもの」ではなく、使い方次第でパフォーマンスを引き出す栄養素です。目的に応じて食べ分けることで、日常生活からスポーツの試合まで、力を発揮できる体に近づきます。
👉 脂質の多い揚げ物やクリーム系は避け、消化の良い食事を心がけることがポイントです。
対象別に分けて解説
🏃 市民ランナー向け:フルマラソン前のカーボローディング
市民ランナーの多くが直面するのが「30kmの壁」。これは体内のグリコーゲンが枯渇して、脂肪代謝に切り替わることでスピードが落ちる現象です。
ここでカーボローディングを行えば、後半まで失速せず走り切れる確率が高まります。
実践ポイント
- レース 2〜3日前から主食を増やす(白米・うどん・パスタなど)
- 揚げ物や脂っこい食事は避ける
- 前日は腹八分目、当日は消化の良いおにぎりやバナナを中心に
注意点
- 過食すると体重増加で逆効果
- 菓子パンやケーキなど脂質の多い食品に偏らない
- 初めて挑戦する場合は練習レースで試しておく
現場での体験談
接骨院に通っていた市民ランナーの方にカーボローディングを指導したところ、「初めて35kmを過ぎても足が止まらなかった」と喜ばれていました。
🏀 部活生向け:試合や合宿でのカーボローディング
高校生の部活(野球・サッカー・バスケなど)は、試合が何試合も続いたり、合宿で練習量が急増したりします。このときにエネルギー不足になると、怪我や疲労の原因に。
実践ポイント
- 試合の前日夜は ごはんやうどんを多めに
- 朝食は 消化の良いおにぎりやバナナ
- 合宿では 間食に果物やおにぎり を取り入れてエネルギーを途切れさせない
注意点
- 揚げ物やラーメンなど脂質が多い食事は動きが重くなる
- 食べ過ぎで腹痛や下痢になるケースがあるので腹八分目
現場での体験談
私がトレーナーをしていた高校野球部では、合宿前に「揚げ物禁止・ごはん中心」に変えたところ、後半のバテが大きく減りました。選手自身も「最後まで足が動いた」と実感していました。
👵 高齢者向け:体力維持のためのカーボローディング的工夫
高齢者は「大会前に特別な準備をする」ことは少ないですが、日常生活の持久力や体力維持にも炭水化物の摂り方は影響します。
実践ポイント
- 朝食に ごはん+味噌汁+少量の魚 を基本に
- 散歩や運動の前に バナナや小さなおにぎり を取り入れると疲れにくい
- 夜は おかゆやうどん など消化にやさしい炭水化物を
注意点
- 糖尿病や血糖コントロールに課題がある人は、医師の指導を受けて調整する
- 食物繊維が多すぎると消化に負担がかかる(玄米は少量から)
現場での体験談
体育館での高齢者健康教室で、運動前にバナナ半分を食べてから参加してもらったところ、「今日は最後まで疲れにくかった」という声が多く聞かれました。小さな工夫でも大きな違いが出ます。
対象別に工夫して「燃料を貯金する」
- 市民ランナー → レース3日前から炭水化物を増やす
- 部活生 → 試合・合宿で米やうどん中心に切り替える
- 高齢者 → 散歩や運動前に軽く炭水化物を摂って体力維持
カーボローディングとは、単なる「炭水化物を多く食べること」ではなく、身体の燃料タンクを満タンにするための準備。対象や目的によって工夫の仕方は違いますが、共通しているのは「質とタイミングを意識すること」です。
現場での体験談
高校野球部の合宿
試合前に従来どおりのラーメンや揚げ物を控え、米やうどんを中心にしたところ、後半のバテが激減。「最後まで足が動いた」と選手自身が驚いていました。
接骨院の市民ランナー
フルマラソンに挑戦する患者さんにカーボローディングを勧めたところ、「30km以降も失速せず走れた」と報告を受けました。トレーニングだけでなく食事戦略が結果に直結するのを実感されたようです。
注意点:やりすぎは逆効果
カーボローディングでよくある失敗は「炭水化物を大量に食べればいい」と思って過食してしまうことです。
- 食物繊維を摂りすぎると消化不良や腹部の張りを招く
- 菓子パンやケーキなど脂質の多い炭水化物は胃もたれの原因になる
- レース直前に食べすぎると消化が追いつかず、逆にパフォーマンスを落とす
あくまで 適量を、消化の良い形で 摂ることが大切です。
まとめ:炭水化物を味方にする食事戦略
- 炭水化物の質とタイミングで持久力は大きく変わる
- レース前はカーボローディングでグリコーゲンを最大限蓄える
- 消化の良い炭水化物を中心にし、脂質は控える
- 無理な糖質制限はスタミナを奪うリスクがある

「走りきれない」「試合の後半で動けなくなる」と悩む選手でも、炭水化物を正しく摂るだけで最後までパフォーマンスを維持できるようになります。トレーニングと同じくらい、食事も勝負を決める大事な要素なのです。
新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市
#炭水化物の摂り方 #持久力アップ食事 #カーボローディング #グリコーゲン補給 #スタミナアップ方法 #運動前の食事 #運動後の食事 #スポーツ栄養学 #マラソン食事法 #試合前の食事